<<一番身近な税金「消費税」>>

こんにちは、経理部の川口です。
買い物をしたり、サービスの提供を受けたりした時にかかる消費税。
私達の一番身近な税金といっても過言ではないと思います。
今回は私達の一番身近な税金「消費税」についてお話させていただきます!
消費税が導入されたのは1989年(平成元年)4月1日。当時3%からスタートしました。
その後、1997年(平成9年)4月1日に5%、2014年(平成26年)4月1日に8%、そして、記憶に新しい2019年(令和元年)10月1日に10%(軽減税率8%)と上がり続けてきました。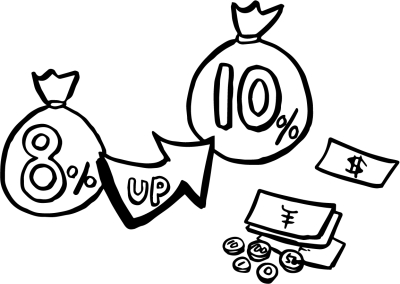
消費税が無い時代があったなんて驚きですね。導入までの国民の反発は凄まじいものだったと想像できます。
国民の反発を押し切り、なぜ消費税は導入されたのでしょうか。
消費税が導入された大きな理由の一つが、日本が抱えている高齢化社会の問題です。2025年現在、国民の約3人に1人が65歳以上、約5人に1人が75歳以上になると言われ、超高齢化社会を歩み続ける日本。
政府は現役世代に頼った税制では、今後、働き手の税負担が限界に達し、事業意欲や勤労意欲を阻害してしまうと懸念しました。消費税は消費全体に広く薄く負担を求める税金であることから、高齢化社会の問題が消費税導入の追い風となったようです。
ここで消費税の仕組みを簡単にお話させていただきたいと思います。
消費税とは、消費一般に広く公平に課税する間接税です。
消費税が課税される取引要件は下記4つの要件を全て満たす取引になります。
【消費税課税要件】
①国内取引であること
②事業者が事業として行うものであること
③対価を得て行うものであること
④資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること
原則として国内取引の全てが課税対象となりますが、消費税は消費に負担を求める税ですので、社会政策的配慮から課税の対象外とする取引もあります。例えば、身近なものですと預貯金の利子や保険料、また、学校の授業料や入学金等も消費税はかかりません。消費税がかからない取引を非課税取引と呼びます。
ところで、間接税ってなんだったっけ?と思った方もいらっしゃるのでは。
ここで、直接税と間接税について補足いたします。
直接税…税金を負担する人と納める人が一致します。
例えば、所得税・法人税・相続税・住民税等が直接税にあたります。
間接税…税金を負担する人と納める人が異なります。
例えば、消費税・酒税等が間接税にあたります。
消費税は消費者が負担し、事業者(個人事業者・法人)が申告、納付します。
個人事業者…課税期間 1月1日~12月31日 → 翌年3月末までに納付
法 人…課税期間 事業年度 (例)4月1日~3月31日
→ 課税期間終了後2ヶ月以内 (例)5月末までに納付
事業者は売上にかかる消費税から仕入にかかる消費税を控除して計算し二重に税が課されることはありません。
これを「原則課税」といいます。
簡単にではありますが、消費税の仕組みをお話させていただきました!いかがでしたでしょうか。
少しでも税金の仕組みを理解するきっかけになりましたら幸いです。
経理部 川口



